なかなか上達しないゴルフ。それって全てあなたのせいですか。それともあなたの使っているゴルフクラブのせいですか?
多くのゴルファーが上手くなれないのは①ゴルフが難しい、②自分にゴルフのセンスがないと考えているのではないでしょうか?
もちろん、ゴルファーの皆さんが、極めて単純な表現(一文節に収まるような言葉ですべてを片付けること)に慣れ親しんでいることは知っていますが、すべての責任が何か一つのことにあるというような短絡的なことをお伝えする気は毛頭ありません。
なぜなら、ゴルフは皆さんが頭で理解している通り、とても複雑なゲームと言うだけでなく、人間がパフォーマンスをするということ自体が、それほど単純なことではないからなのです。
しかし、ゴルフを単純に分析してみると、2つの要素によって構成されていることが解ります。
あなたのパフォーマンスと
使用する道具であるゴルフクラブです。
あなたのパフォーマンスに関する説明は他の読み物に譲るとして、ここでは、果たしてあなたが使っているクラブはあなたのパフォーマンスにプラスなのかマイナスなのかということについてお話ししていこうと思います。
ゴルフというゲームにおいてのゴルフクラブという道具の役割は、他のスポーツと比べて極めて大きなものであることは間違いありません。
ルール上14本の使用が認められ、それぞれの道具の役割がある程度明確で、それを駆使して最小のストロークで18ホールをプレーするというゲームですから、例えば100M走のように、フィジカルなパフォーマンスが圧倒的な要素を決定する競技で、どんなスパイクを履いたら早く走れるのか?という要素よりも、ずっと大きな役割を担うことは間違いありません。
であれば、ゴルファーにとってありがたい道具の考え方は、人間のパフォーマンスをより効率よく引き出してくれるもの。
更に言えば、どの番手を用いても、自分自身は同じパフォーマンスをしさえすれば、結果として各番手の役割を果たしてくれるものという発想に至るのは当然のことなのです。
では、果たしてクラブメーカーはそうした観点からゴルフクラブを真剣に開発、製造しているのでしょうか?
皆さんもご存じのとおり、毎年毎年、クラブメーカーは『最新の』『進化した』ゴルフクラブを発売しています。そしてその宣伝文句にはとても魅力的な言葉が書かれていますよね。
より大きな飛距離をもたらす、とか、よりミスし難いなど、ゴルファーにとってはとても魅力的な宣伝文句です。
笑い話では、「過去の宣伝文句をそのままできてたら、今頃は軽々500ヤード+のティショットを、いつも真っ直ぐ打ててるよね」などと言うのも今は昔。今では、宣伝文句も「また言ってるよ」ぐらいにしか受け取られずに、ガンダムのようにカチカチといろんなところを調節して、最適の一本を自分で見つけるなんて無責任な製品にまで発展してしまったのです。
果たして、ゴルフクラブと言うのはクラブメーカーが宣伝文句で繰り返し言い続けているほど、進化しているのでしょうか?
ヘッドの素材を替え、クラブの長さを変え、ヘッドのサイズを変え、シャフトを軽くし・・・
やれ高反発が飛ぶ。でも、ルールで認められなくなったから、低反発にしろと言う。
そうした宣伝文句の効果が薄れてくると、今度は少し短くして、ヘッドを小さめにする。
次は、ヘッドに装着する錘の重さと位置をゴルファーが勝手に調節できるようにしたり、フェース角やライ角を調節できるようにして、最適なクラブをあなたになんてことが進化だと平然と言っているのです。
実際、もう弄るところが無い。飽和状態なのです。
そもそも、ゴルフクラブを形成しているのは基本的に3つのパーツしかないのですから。ヘッド、シャフト、グリップ。そして、各々にルールで定められた規格が存在するのですから、弄るところは限られて当たり前なのです。
これまでのゴルフクラブの発想の枠で考えている限り、近年、自動車業界に起こっているハイブリッドでパフォーマンスと燃費の両立をなんていう、おおきな変革はもたらし難いのは確かなのです。
また、ゴルフクラブは多くの場合、『飛び』という点にフォーカスが置かれ、その点ばかりを強調して語られているのですが、果たして、その開発のコンセプトそのものに問題はないのでしょうか?
その前に、少し雑談(というか、本質ですが・・・)にお付き合いください。
皆さんの頭の中では、ゴルフクラブは年々進化しているものとして存在しているのでしょうが、実はそうでもないのです。
ご存知のように、ゴルフクラブにはスウィングバランスという指標があります。C8とかD0とかいうやつです。
男性用クラブだと、D0合わせと言うのが『標準的』となっていますが、そもそも、どうやってスウィングバランスを測定しているのかご存知ですか?
ご存知のない方は、ミズノのクラブオーダーサイトで説明されていますから、ご覧になってみてください。
http://www.mizunoshop.net/cluborder/static/function/about_balance.html
モノの測定には原則が有って、そのモノが使用される状態で、或いはその状態をシミュレートした状況下で測定するということです。
上記のサイトを訪れるとバランス計の写真がご覧になれますが、問題は、ゴルフクラブって止まった状態で水平にして使うものなの?と言うことです。
クラブメーカーやゴルファーの皆さんがこだわっているスウィングバランスって本当に有効な指標なのかどうかと言う根本的な、そして大きな疑問が存在しているのです。
メーカーの宣伝文句には物理的や、科学的に凄くすぐれているような文言が羅列されていますが、そもそも根本に存在するゴルフクラブの構造の基準が実際に使用される状態とは全く似ても似つかない状態で測定された指標によって制限されているということ自体が「どーなのよ?」ということです。
そして、このバランス計、多少の改良を加えられたとはいうものの、基本的には1920年代前半に作られたものなのです。殆ど1世紀前のコンセプトですよ!!そのコンセプトを制限として作られ続けているモノが、どれだけ進化したところで、大した進化をもたらすことにならないのでは?と考えるのが普通なのではないですか?
そして、そのコンセプトは未だにクラブメーカーのクラブ作りの『制限』、或いは『大前提』として存在しているのです。その枠の中でクラブ開発をする、新しいクラブを作るということですから、もちろん、前述のように弄るところは限りなく制限されてしまうのです。
この測定方法、クラブメーカーやゴルフショップにとっては、とてもありがたいものなのです。手前勝手と言っても良いくらいのものなのです。なぜなら、3つのパーツをいろいろ弄っても、最終的にネック(あるいはバット:グリップエンドですね)に錘を装着して、『バランスを合わせる』ことで、『正しい』クラブになるという魔法の方法なのですから。
先述したように、このゴルフクラブのバランスの測定方法は「測定の原則」に背いているわけですから、そもそも意味がない、というか、実際の使用状況においてのバランスが合っていないということの証明以外の何ものでもないのです。
考え方はさておき、具体的には、大きな2つの問題が存在します。
一つは、長いものほど、振り難くなるということ。
もう一つは、例えば、300gのクラブでも3kgのクラブでも、同様にバランスが合っているということになってしまうということなのです。
平らに言うとつまり、ゴルファーが同じ動きをしても、クラブ毎の機能を発揮してくれないということです。
この影響、皆さんは知らず知らずのうちに体験し、多くの場合、自分自身のパフォーマンスに疑問を抱くことで納得しているのではないでしょうか?
例えば、アイアンが調子が良いと、ウッドが打てない。なので、ウッドを練習して打てるようになるとアイアンの調子が悪くなる。
全てとは言いませんが、こうした問題の多くは、クラブに責任があると考えられるのです。
そもそも、人間が使う道具であるにも関わらず、クラブ開発においては、殆ど人間の動きをより効率を高めるものを作るということは考えられていないのが現実なのです。
『最近のクラブはこう打つ』などと言う、レッスンが存在するのも、考えてみればおかしな話なのです。『このバットの打ち方』とか、『このサッカーシューズを履いたら、ボールをこう蹴れ』、『この包丁で千切りを上手く切るにはこう切れ』みたいなものでしょう?
普通であれば、発想が逆だと気づくはずなのです。人間が効率の良いパフォーマンスをするパターンと言うのは存在しています。そして、そのパターンをよりやり易いように、そして、非効率的な動きをやり難いようにするのが「良い道具」と、考えるはずなのです。
しかし、ゴルフクラブの開発にはそうした考え方は存在していないのです。
なぜなら、ゴルフそのものの発想が、極めてズレて考え続けられているからなのです。
長い棒の先に錘がついた道具を振り回すわけですから、結果として表面上に現れる形は、実際に人間が行っている動きとは大きく異なることは物理的事実ですから無視しようがないことなのです。
釣竿を思い浮かべてみれば簡単に解ると思いますが、釣竿を振る感じと、結果として竿がしなる感じや「錘」や「うき」が動く感じとの間には、おおきなギャップが存在します。釣竿ほど極端ではないですが、ゴルフスウィングも同様のことなのです。
これ、物理的、数学的には答えが得られないのです。なぜなら、クラブヘッドの持つ力の大きさは、スウィングのスピードによって大きく変わるから、或るスピードでバランスが合っているから、それでバランスが合っているかというと、そうではないということなのです。
MOIマッチングという方法が存在しますが、あれも、結局のところクラブの物理的特性だけを異なる方法で測定しているという思想の範囲内での工夫ですから、プロリスミック計よりは多少良いのですが、それほど大きく変わるものではないのです。
結局のところ、人間が使う道具の開発のコンセプトに、人間の動きの特性や人間の機能的な要素がほとんど(全くではないにしても・・・)考慮されていないと言うことなのです。
加えて、ゴルフクラブという道具は、番手によってその用途が異なります。
ドライバーのような長い番手は大きな飛距離を出したいということが念頭にあるでしょう。
一方、ウェッジでは、飛距離よりも、正確性や操作性を重視する番手であることは周知の事実です。
であれば、同じ指標を使って、同じコンセプトで開発をするということそのものに、普通であれば違和感を覚えるものなのですが、ゴルフクラブではそうした普通の発想さえも指摘されてないのです。
過言ではなく、こうした思考よりも、バランスを合わせるということの方が、圧倒的に優先される要素なのです。
そして、大きな問題はこの『バランスを合わせる』という考え方が、確固たる思想からの有利性を前提とした判断から使われているのではなく、『ゴルフクラブとはそういうものだから』という、慣例的な要因によって選択されているということなのです。
ゴルフレッスンにおいて、結果的な形を説明することがゴルフのレッスンであるという、確固たる判断基準も存在せず、ただ『そういうものだから』と言う理由のみで、何十年もそうした方法を使い続けているのがゴルフなのだと疑って考えなければいけないのかもしれません。
そして長きにわたって根本的な道具としての考え方は全く変わらないままに、部品(と言っても基本的に3つのパーツですが)を別々に、それも物理的な特性ばかりを『研究』し、それをしてゴルフクラブが進化し、あなたのゴルフの上達に役立つものであるとされてきているのです。
実際、1970年代にはほとんどのクラブにスティールシャフトが装着され、アイアンンのヘッドは鍛造、ウッドは木製でした。
そしてもちろん、ゴルフをプレーするすべての年代がそのクラブを使ってゲームを楽しんでいたのです。
グラファイトシャフトが登場し、スティールヘッドやチタンヘッドが登場し、クラブを軽く長く組み上げることが可能になって(もちろん前述のバランス計の原則に則ってと言う意味での可能です)、軽ければ振り易い、長ければヘッドスピードが速くなるから飛距離が出るという、人間の機能を全く無視した短絡的な発想のみによるクラブ開発が何十年も行われてきたのです。
もちろん他の多くのゴルフ関連のことと同様、明記をされることは決してありませんが(たぶん、そもそも、そうしたことを考えていないから、明記をするという発想も生まれないのでしょうが・・・)こうした短絡的な発想の大前提として、長くても、軽くても、『人間の動作に影響を及ぼさず、同様の動作を実行する』というものがあるのですが、実際にはそれが前提として成り立つのかについては考えられることもなく、易しく飛ばせるクラブとしてゴルファーの手元に届いているのです。
そうしたクラブの台頭により、ゴルファーはより怠惰な動作によってボールを飛ばすことが『可能』になってしまったのです。
もちろん、誰でもがその恩恵にあずかることができると言っているのではありません。
たまたま、上手く打てた時には、これまでのクラブよりも距離が出るということなのです。
人間は適応する生き物です。
そして、残念ながら、楽な方へ適応するのは、大変な方へ適応するよりもずっと簡単に起こってしまうのです(もちろん目先の、短期的なと言う意味においてです)。
そしてそれは、人間の本来の力の出し方、効率の良い動きの質からは離れて行く傾向が強く、結果的に動きそのものは、クラブメーカーの言うところの『クラブの進化』と比例して退化してゆくことになってしまったのです。
近年、年齢とともに、急に飛距離が落ち、それまで打っていたパターンの動作を行うことすらできなくなり、ゴルフを早い年齢に辞めてしまわれる方が少なくありません。
また、若者の中にも、ゴルフによる腰痛が原因でゴルフを続けられなくなってしまっている人も少なくありません。
人間の動きや機能を専門分野とする私から見ると、そうした問題と近年のゴルフクラブの特性と言うのは、どう考えても無関係とは考えられないのです。
もちろん、物理的には正解を導き出すことができないゴルフクラブの物理的特性も、そこに人間の機能や特性に関する知識を加えることによって、少なくとも、既存のゴルフクラブよりも圧倒的に道具として優れているものを作成することは可能なのです。
私の主宰するGolfin’ Dawnでは、こうした考え方に則り、一人一人のゴルファーに合わせて、これまでのバランスや重さの制限にとらわれることなく、人間としての正しい動きを効率よく引き出すゴルフクラブを作成しています。
試打会で打ちやすいと感じ購入し、自分のものとなったとたんに、大した機能を発揮することもなく、押入れの隅に追いやられたクラブは無数に存在しているのではないでしょうか?
実際、中古クラブ屋さんの店先を覗くと、信じられないほど多くのクラブが飾られているではないですか!!
そして、そのチャンピオンがドライバーであることは紛れもない事実なのです。
なぜなら、既存のゴルフクラブの考え方の歪みが最も大きくパフォーマンスに影響を与えるクラブがドライバーだからなのです。
しかし、そうしたクラブをある程度生き返らせることは可能なのです。
本来はすべてを一から考え直し、作り上げることが理想ですが、すでに手元にあり、たいして役に立たなかったクラブを調整し、あなたの動きをより良い方向へ導く道具として生まれ変わらせることができるのです。ご興味のある方はご連絡ください。
どれだけ練習に勤しんでも・・・
やろうとしていることがそもそも間違っている
正しいことを実行するよりも、怠惰な動きで打ててしまう道具を使用する
という、2つの大きな問題点とお付き合いしながらでは、上達するわけがないのです。
レッスン記事だけでなく、ゴルフクラブの宣伝文句も鵜呑みにしてしまうゴルファーが少なくないのは紛れもない事実です。
あまりにもオイシイ話だから、そんなことは無いよなと考えるものの、ではどうしたら良いのか?については明確な答えが無いので、結局のところ、クラブメーカーの言う『進化したクラブ』に食指を動かすことでお茶を濁してしまっているのではありませんか?
もちろん皆さんが上手くなりたいと思っている気持ちには嘘偽りがあると言っているのではありません。
皆さんがとても真剣に上達したいと願っている気持ちは痛いほどわかります。
であればなおさら、なんでも鵜呑みにして受け入れるということを辞めなければ、努力が無駄になるどころか悪癖を身に付け、ゴルフ人生をつまらなく、短いものにしてしまう危険性さえあるのですからお気を付けください。
科学的なものの考え方にはとても有効なものがあります。
明確な理由が存在しないものは信じるな。
明確すぎる結論には気を付けろ。
と言う2つの法則です。
特に人間という複雑なシステムが関与しているゴルフと言うゲームでは、断定的に言いきれるような要素は存在しないと考えても問題はありません。
例えば「AはBである」とか、「Cすれば必ずDになる」的な断定的なものは、ほぼ嘘だと疑ってかかって良いと思います。
私は皆さんが上達をめざし、努力をするのであれば、その努力に報いる結果を引き出してもらいたいと持っているのです。
本当に信じられないくらい既存のゴルフの常識には科学の非常識がたくさん存在しているのです。
ゴルフってそういうものと鵜呑みにしてしまうことで、自分自身のゴルフ人生が暗闇の中でもがき苦しむものになってしまうことになるかもしれないのです。
楽しみとしてやるからこそ、本当に楽しくできるようにいろいろなことを真剣に考えてほしいのです。
氾濫する情報に惑わされることなく、自分にとって有意義なことを適切に判断し取り入れ、効率よく活用できるゴルファーになってほしいと願っているのです。

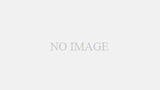
コメント